衝動Ⅱ~タンバリンリン~ by塩見岳大

日時:令和2年11月23日
執筆者:塩見岳大
タイトル:衝動Ⅱ~タンバリンリン~
2012年、
アマチュアだった僕達が剥き出しの情熱を、
燻っていた激情を曝け出したツアー「衝動」。
それから3年、
僕達はプロとして飛び出し、
環境は変わり、
見る世界が変わり、
求めるものが変わりました。
そして、プロとしてのステージに求めた最初の大きな変革が、
「衝動Ⅱ」にはあったように思います。
僕達にとっての和太鼓は、
自らを表現するためのツールです。
信号や文字、言葉のように、
僕達の感情を、世界を表現するためのツールが和太鼓だったのです。
和太鼓奏者が和太鼓を用いて自らを表現する。
そこに歪みはないとは思います。
しかし、それをお客様に届けるための装置としての舞台、
純粋な想いをより高い純度で表現するための舞台作りというものに一層力を入れ始めたのが和太鼓彩結成10周年ツアー「衝動Ⅱ」だったように思います。
初めての全国ツアーということもあり、
この公演にかけた作り込みは凄まじく、
それには僕達の舞台上での意識改革も含まれました。
僕達の公演は自由奔放でした。
公演の中にどんなアドリブを入れても許され、
僕達は自由気ままに舞台上で暴れ回っていました。
そういった舞台の面白さを僕は知っているし、
そういった舞台の危うさも僕は知っています。
しかし今回、
衝動Ⅱでは完成された一つの「作品」を作り上げるために、
演者の行動を規定し、
本能と直感の赴くままに感情を曝け出す舞台ではなく、
和太鼓奏者が作り上げる世界を作品としてお客様にお届けする、
そんな舞台を目指して作りました。
これだけ言うとメンバーが窮屈な制限を受けて機械的な表現をするような印象にも聞こえますが、
そうではなく感情を曝け出すシーンでは存分に感情を曝け出し、
静寂を尊ぶシーンではそれに従い、
明るくハッピーなシーンでは最高の笑顔を披露する。
そういった一つ一つのシーンの方向性を細かく定め、
練習を重ね、修正し、それを積み重ねていく。
当たり前のことなのですが、
それを一挙一動一言までに落とし込み、作り込んでいったのが、
「衝動Ⅱ」という公演でした。
全ての演目で議論を重ね、
稽古を重ねていったのですが、
その過程でぶつかった壁の一つを今日はお話ししたいと思います。
先んじて、どの曲でその壁にぶつかったのかを申し上げます。
「タンバリンリン」です。
今日は比較的真面目な文体ですし、
「衝動Ⅱ」における「奏」の想いなどを語るのかと思った方もいらっしゃるかもしれません。
残念!タンバリンリンです! 笑
いつか「衝動Ⅱ」の「奏」についても、
あふれる想いはあるので書いてみたいものですが、
今日はタンバリンリンです。
さて、タンバリンリンという曲を語る前に、
まず僕というキャラクターがどのように出来上がったかを簡単に話す必要があります。
舞台上の人間としてではなく、
普通に生活する人間としての僕は、
お察しの通り根っからのいじられキャラ、オチ要員、ヒエラルキー最下層の守護者でした。
しかし当初、
舞台上ではあまりそう言ったことを表に出す機会はありませんでした。
それを表に出すようになったのは和太鼓彩がストリートでの演奏を多分に行っていた頃、
まだ演奏を告知しても、それを見に来てくださるお客様がいなかった頃です。
ストリートの演奏で少しでも歩行者の目を引くために、
自分のキャラクターを公演中に出していくようになりました。
完全にアドリブです。
その頃の和太鼓彩の演奏はいきなりMCが割って入ったり、
突如演目を変更したり、配置を変更したりとアドリブ合戦の様相を呈するところもありました。
それはストリート演奏という環境の中で、流動的なお客様の心を掴むために得た彩なりの解答だったと今では思います。
しかしやはり、ストリートでの演奏を重ねてきた当時の彩メンバーにはその経験と成果が積み上げられていたので、その風潮をホール公演などに持ち込むこともありました。
特に和太鼓彩における「お笑いパート」では大まかな筋書きを作っておき、
本番はその大筋だけは守りつつ各々が暴れ回ることが多かったです。
しかし、
今回は「ホール」で「作品」を作るという決め事の中、
齋と僕で「お笑いパート」を制作することが決定いたしました。
これは難しい。
当時は心底そう思いました。
公演の中で抑揚をつけるためにこういった「お笑いパート」は大事だと思っています。
長い公演の中でお客様に一度肩の力を抜いていただくことによって、
その後の演目における静寂や迫力がより際立つと思いますし、
エンターテイメントとして「面白い」の幅を広げることにもなると思います。
しかし、今までの僕達の「お笑いパート」ではなく作品としての「お笑いパート」を作り込むためにはどうすれば良いのか。
齋と二人で、あれでもなければこれでもないと意見を交わしながら、アイデアを作っては捨て、作っては捨て…
そんな中、完成したのが「タンバリンリン」の「作り込んだお笑い」でした。
お客様にいつ、どのタイミングで笑っていただきたいのか。
この展開が何故面白いのか。
その場のアドリブとノリと勢いではなく、
全てを一から十まで作り上げ、
作品としてお客様に「お笑い」をお届けする。
タンバリンリンという演目は派生作品も多く、
一見チャランポランな演目に見えますが、
当初はそんな想いを胸に作り上げた楽曲なのでございます。
一言一句、一挙一動、
細部まで細かく決め込みました。
お笑いの議論というものは少し小っ恥ずかしいもので、
自分が面白いと思った言動の理由と意味を解説しなければならないというのは、
なかなかメンタルを削られるものがありました。
なので、タンバリンリンのこの言動はこういう狙いがあって、
この展開はこういう目算があって考えた…なんていう解説はできません 笑
タンバリンを片手に、齋と二人で練習後に通ったカラオケの店員さんは、
いつも歌いもせずにタンバリンを鳴らして騒ぐ、なんて愉快な人達だろうと思ったに違いありません。
本番の初タンバリンリン披露は想像以上に緊張しました。
アドリブと勢いで暴れる「お笑いパート」ではなく、
今回は全ての言動を細かく決めたショーです。
手汗を握りしめながら、
完璧に暗記して反復した立ち振る舞いを、
本番直前まで確認していました。
そして、ただテンションを上げるのではない。
ただ自分を曝け出すのでもない。
そのショーの登場人物としての塩見岳大に成り切るのです。
自分によく似た、しかし別の人間になるような心持ちで、
作り上げたキャラクターの中にダイブしていきます。
そして僕はただ自分を曝け出す楽しさだけではなく、
作り込んだ作品を披露する楽しさを覚えました。
衝動Ⅱのタンバリンリンを通して、
それまでのお笑いパートの新しい形の変化を感じていただけたのであれば僕達は本望です。
しかし、もしタンバリンリンをご覧いただく機会があれば、
言動の意図や、展開の意味などを深く考えていただくのはよしていただきたい 笑
肩の力を抜いて、頭の中をすっからかんにして、
気楽に楽しんでいただければと思います。
またタンバリンリンを披露する日を是非、楽しみにしていてください!

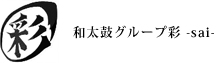





この記事へのコメントはありません。